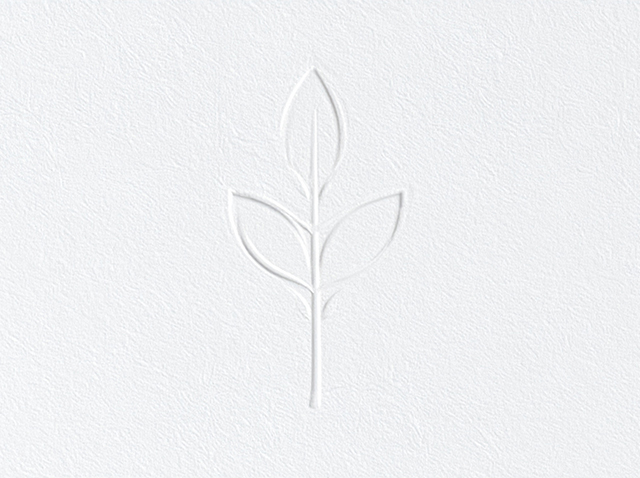デザイン・印刷・製本・用語紹介 PART2
honsawa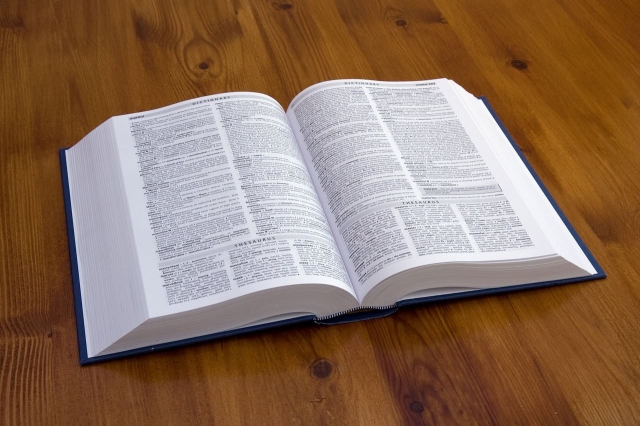
前回につづき、デザイン・製版・印刷・製本などに関する用語を一部紹介します。
<お>
【奥付け】製本
書籍や雑誌の最後に書名・著者名・編集者名・発行者名・発行所名・定価などをまとめて記したページあるいはその箇所のことを言います。
【折り】製本
印刷されたものを製本するために頁順に折りたたむことです。または、折ったものです。16頁分の8つ折りの他、8頁分の4つ折りなどがあります。〔類〕折り丁
【折り込み】製本
本の大きさより大きい紙を折りたたんで、本に綴じてあることです。目次や図表・写真などに見られます。片観音、両観音折りはよく使われます。
【折り丁】製本
折りの終わった印刷物のことです。普通はひとつの折りが16頁で1単位(1台または1折り)となっています。
【観音折り】製本
本の大きさよりも大きい紙を2つ折りにして、折り込んである状態のものです。特に左右対称のものを「両観音」、片面だけを「片観音」と言います。
<き>
【菊判】用紙
A列本判よりやや大きいJIS規格外の原紙寸法の636×939mm。あるいは菊判原紙を16裁した寸法150×220mmを指します。
【逆目】用紙/製本
紙には目があり、製本した時には天地の方向に紙の目が通っているように使うのが基本ですが、それとは反対に背に直角に目が通っていること。この場合、本だと波をうって開けにくく、耐久性も落ちます。
<く>
【くるみ】製本
本の中身を綴じてから、表紙を裏表1枚でくるむようにして接着し、表紙と中身を一緒に化粧裁ちしたものです。〔同〕くるみ表紙
【くわえ】印刷
用紙が印刷機の中で送られる際、機械の爪がかかる部分。くわえの部分は印刷できず、ここは化粧裁ちによって落とされます。〔同〕くわえ代
<け>
【罫】指定
線の総称の罫には太さ・形状に応じて様々な種類があり、単に罫としただけでは指定にはなりません。
【ケイアタリ】指定
指定のために引いた罫が、仕上がりの時には必要でない場合、「ケイアタリ」・「ケイアタリのみ」と指定します。〔同〕アタリケイ
【見当合わせ】印刷
2色刷り以上のカラー印刷や紙の両面に印刷をする場合など、各刷版が印刷される位置関係を合わせること。見当が合わなければ版ズレが起こります。〔同〕トンボ合わせ
<こ>
【校正紙】
校正をするための刷り物。関係者だけに見せるために、少部数しか刷りません。〔同〕校正刷り
次回へ続く