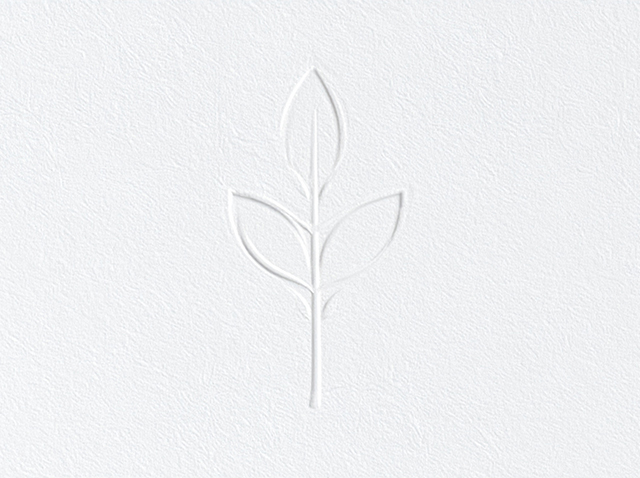印刷豆知識
印刷における塗り足しとは?塗り足しが必要な理由も解説!
kaneko
印刷の用語である「塗り足し」という言葉ですが、「裁ち落とし」とも呼ばれます。
古くから業界では使われる言葉ですが、一般の方にとってはあまり聞きなれない言葉かもしれません。
そこで今回は、印刷物に必要な塗り足しについて解説します。
ぜひ最後までご覧ください。
大きな紙に面付された印刷物を最終的な仕上りサイズに断裁します。
その際、仕上がった時の絵柄が紙の端まで印刷されるように(余白が出ないように)「塗り足し」を作る必要があります。
一般に塗り足しは、仕上りサイズより外側に3mm(印刷物によっては3mm以上)余分にはみ出させておきます。
その塗り足しの部分は、断裁時に切り落とされます。 断裁では多少の誤差が生じるものですが、塗り足しが作ってあれば多少ずれたとしても紙の余白が出てしまうことはありません。
塗り足しが無いために、断裁でズレて出てしまった仕上り端沿いの白い線は思いのほか目立ちます。
必要とする塗り足しが無い場合、入稿元で無いと判断や対処できないケースもあります。 (画像などが伸ばせず、拡大などで塗り足し部分まで広げるなど)
このような事態を未然に防ぐためにも、仕上り位置の近隣にあるオブジェクトには、仕上がりを意識し注意して配置する必要があります。
本記事が皆様の参考になれば幸いです。
古くから業界では使われる言葉ですが、一般の方にとってはあまり聞きなれない言葉かもしれません。
そこで今回は、印刷物に必要な塗り足しについて解説します。
ぜひ最後までご覧ください。
塗り足しとは
印刷物には印刷した後に断裁という工程があります。大きな紙に面付された印刷物を最終的な仕上りサイズに断裁します。
その際、仕上がった時の絵柄が紙の端まで印刷されるように(余白が出ないように)「塗り足し」を作る必要があります。
一般に塗り足しは、仕上りサイズより外側に3mm(印刷物によっては3mm以上)余分にはみ出させておきます。
その塗り足しの部分は、断裁時に切り落とされます。 断裁では多少の誤差が生じるものですが、塗り足しが作ってあれば多少ずれたとしても紙の余白が出てしまうことはありません。
塗り足しが無いとどうなる?
入稿時のデータ不備で多いのが、塗り足しや仕上り領域に関するものです。塗り足しが無いために、断裁でズレて出てしまった仕上り端沿いの白い線は思いのほか目立ちます。
必要とする塗り足しが無い場合、入稿元で無いと判断や対処できないケースもあります。 (画像などが伸ばせず、拡大などで塗り足し部分まで広げるなど)
このような事態を未然に防ぐためにも、仕上り位置の近隣にあるオブジェクトには、仕上がりを意識し注意して配置する必要があります。
まとめ
どうしても塗り足しが伸ばせない場合は、いっそのこと天地左右に3mm程度の余白を設ける程度に全体を縮小してしまう方法もありますが、この場合でもやはり入稿元に判断を仰ぐことになりますので、その手間をかけないためにも最終イメージを把握したデータ作りが大切です。本記事が皆様の参考になれば幸いです。
私たちはお客様のビジョンを実現するために、安価な印刷、高品質な印刷、オンデマンド印刷、オフセット印刷などお客様に合った提案をさせて頂きます。
印刷物はもとより「デザインはよくわからない」という方もご安心ください。
ご要望に沿ったプランをご提案させていただきます。
制作からきめ細かいサポートを含めた幅広い印刷サービスをご提供します。
東京都千代田区を中心に都内全域で「印刷」のことなら、フジプランズへお任せください。
お問い合わせは、
お電話またはメールにて承ります!
お電話の場合はこちら:
03-5226-2601
メールの場合はこちら:
お問合せ専用フォーム
サービスメニューについてはこちら:
サービス内容